「パワハラによる自殺や精神疾患が社会問題になっている」
といった文言を見ると、身につまされる人も多いのではないでしょうか。
会社勤め人であれば、多かれ少なかれパワハラを受けた経験のある人もいるでしょう。
会社はピラミッド状の組織構造になっており、上位者が下位者に対して権力や権限を行使するなかでパワハラは発生します。
会社組織で働いている以上、パワハラを受ける可能性は誰もが持っています。
では、あなたがパワハラを受けるかどうかは何によって決まるのかと言えば、
それは『上司』です。
会社員の最大のリスクは上司を選べないことだと言いますが、まさに上司に恵まれなければパワハラを受ける可能性があるということです。
ということは、自分の力でパワハラから免れようとしても無理だということです。
そして、運悪くパワハラを受けるような状況に陥ってしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
パワハラ問題はいったん起きてしまうと、解決するのが本当に難しい。
そのため、パワハラを受けることになったならば、退職を含めた極めて難しい選択を迫られることを覚悟しなければなりません。
今回は、あなたがパワハラを受けた場合のとるべき対応策について説明します。
パワハラを受けたときは「運が悪かった」とあきらめよう。

パワハラを受ける可能性は、会社員であれば誰でも等しくあります。
それはパワハラをおこなうのは上司であり、その上司を選ぶことができないからです。
すべては運を天に任せるしかありません。
そして、実際にパワハラ上司に当たってしまったときは「運が悪かった」と思って諦めるしかありません。
パワハラには多くの種類があります。
怒鳴ったり、殴ったり、蹴飛ばしたりといったような激しい言動を思い浮かべる人もいるでしょうが、そういった種類のパワハラは数的には少ないでしょう。
それよりもむしろ、地味なパワハラのほうが圧倒的に多いですね。
たとえば、挨拶を無視されたり、満足な仕事を与えられなかったり、会議に呼ばなかったりといったようなことです。
こうした種類のパワハラは、実行側の上司にしてみれば、もってこいのパワハラです。
というのも、パワハラ認定が難しいからです。
例えば、仕事を与えないのは能力の問題だと釈明できますし、また、挨拶を無視したのは声が聞こえなかっただけかもしれません。
上司からすれば、パワハラ認定されにくいとなれば、社員に訴えられる心配もなく、パワハラを実行できるというわけです。
一方で、人を殴ったり、もしくは大声で「バカ、アホ、辞めてしまえ!」といった激しいパワハラは100%パワハラです。
そうした言動は周囲の人の目にも触れるため、上司として釈明ができません。
もし、いまあなたがパワハラを受けているとすれば、おそらく地味なパワハラではないでしょうか。
あなたが上司から受けている行為がパワハラかどうかは以下のサイトで確認できます。
・厚生労働省(職場におけるハラスメント防止のために)
問題は、あなたが上司から受けている行為がパワハラにあたるかどうかではなく、あなたが受けている行為に苦痛を感じているかどうかです。
たとえ、上司の言動がパワハラ行為に該当していなくても、あなたが苦痛を感じて仕事を続けることが困難であれば、それは大問題だということです。
パワハラ問題の根本は『感情的な問題』です。

会社員をやっていれば、上司に怒られたり、注意されたりすることは、誰でも経験はあるでしょう。
もちろん、私もあります。
それが、単発で終わるのであれば問題ないのですが、長期にわたって続くとなるとかなり心身をやられてしまいます。
そもそもどうしてパワハラが起こってしまうのかですが、その原因は『上司の人間性』にあります。
上司の人間性が以下のような人であれば、パワハラ上司の要素を持ち合わせていると言ってよいでしょう。
- 感情の起伏が激しい
- 短気
- 精神不安定
- 小心者
そして、上記のような上司に好き嫌いの感情が合わさったとき、パワハラへの言動が開始されます。
パワハラ上司のもう一つの特徴として、好き嫌いの感情が激しいというのがあります。
人は誰でも好き嫌いの感情を持っているものですが、パワハラ上司は嫌いという感情を嫌いな人に対して直接ぶつけてくる傾向があります。
それは怒りという形に限らず、陰湿な嫌がらせ、無視といったようなあらゆる形で嫌いな人へぶつけてきます。
パワハラを受けた場合、逃げる以外に対応策はありません。

パワハラを長期間にわたって我慢し続けるには限界があります。
人はそれほど強くはありません。
私はこれまで、上司の度重なる暴言や嫌がらせを受けて辞めていった社員を何人も見てきました。
はたして辞めていった人たちは正しい選択をしたといえるのか。
他に選択肢はなかったのか。
結論からいうと、正しい選択をしたといえます。
なぜなら、上司からのパワハラに対しては効果的な対応策がないからです。
なかには「パワハラの証拠さえ押さえれば戦えるのでは」といった意見を持っている人もいるでしょう。
退職か?それとも戦うべきか?
正直迷うところではありますが、それでも『退職する』の一択です。
そもそも戦うと言ったって戦う方法が見当たりません。
まさかパワハラ上司に直接文句を言うわけにはいかないでしょう。
それとも、上司の上司に助けを求めに行きますか。
そのようなことをしても、火に油を注ぐだけ。
それは告げ口したことになるので、それを知った上司はさらにパワハラをエスカレートさせることになります。
それこそ逆効果です。
「よし!それでは」と腹を括って労働局に相談にいきますか。
パワハラの明確な証拠を集め、これで解決できると思って行ったはいいが、すぐに労働局の態度に失望することになります。
労働局が動くことはありません。
なぜなら、パワハラは法律で禁止されているものではないからです。
法律で禁止されていないことに対して、国の機関は積極的に動くことはありません。
多少のアドバイスをくれるかもしれません。
もしかすると、親切な職員であれば、あなたの会社に電話して注意くらいはしてくれるかもしれません。
いずれにせよ、パワハラを受けて戦おうとしても戦いようがありません。
あとは、精神の限界まで耐えるしかないということです。
それでも、いつまで精神が持つかどうか。
人事異動のある会社であれば、パワハラ上司とお別れできる可能性があるので多少は心の支えにもなります。。
しかし、中小で人事異動のない会社であれば、もう絶望的です。
そうなれば、心身をやられて働けなくなる前に退職するべきです。
会社は他にもいくらでもありませんが、あなたのカラダは一つしかありません。
一度心身をやられてしまうと、再起するまでに多くの時間を費やすことになります。
下手をすれば、回復すらできないくらいにはやられてしまうことだってあります。
おわりに
このままやられっぱなしでは怒りが収まらない人もいるでしょう。
最終手段は裁判に訴えることです。
裁判に勝てば、いくらかの慰謝料はとれますが、いまの会社で仕事をすることはできなくなります。
パワハラで訴えるということは、上司だけではなく会社をも訴訟の対象にしなければなりません。
会社を相手に裁判をおこして、今後もその会社に居続けることができますか。
現実的には無理でしょう。
訴えても慰謝料を取れるかもしれませんが、元の状態には戻ることはできません。
つまり、訴えることで多少の鬱憤(うっぷん)晴らしはできますが、元通りの状態にはならないということです。
大事なことは、いち早くパワハラ上司の下を去り、次の活躍できる会社をさがすことです。
悔しい思いはあるでしょうが、運が悪かったと思って前に進みましょう。
あなたの能力やスキルが劣化したわけではありません。
ここはスピード感を持って転職活動に入るべきです。
以下は私が活用している転職支援サービスを展開しているサイトです。
転職支援サイトは転職を成功させた人であれば、ほとんどの人は利用しています。
希望の求人情報を無料で紹介してくれるので、是非、活用してみて下さい。
きっとあなたの転職活動を応援してくれます。
何度も言いますが、パワハラに対して我慢し続けると、あなたは再起できないくらいに心身を壊されてしまいます。
健康な体さえあれば、何度もやり直すことはできます。
まずはパワハラから逃れることを考えましょう。
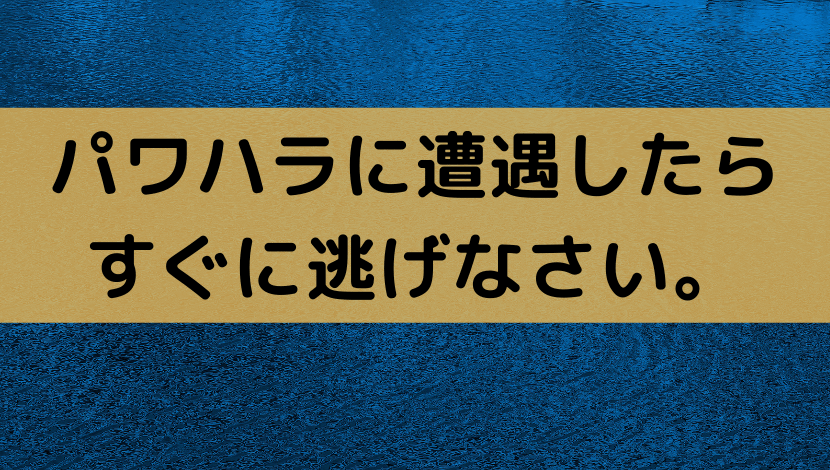
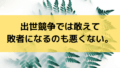

コメント